防災士の日記
行ってきました!震災対策技術展in横浜
こんにちわ!
昨日お知らせいたしました、「震災対策技術展」へ行ってきましたので、その報告をさせていただきます!今日も防災士の木村です。
(昨日予告致しました「消防士さんとの意見交換」につきましては、また後日、アップさせていただきます。)

|
第11回 震災対策技術展冷たい風が吹きすさぶ本日2/2、パシフィコ横浜展示場ホールにて開催されました同展。免震システムや、安否確認システム、耐震マット、エレベーター用の備蓄棚、災害用自動販売機などなど、110を超える企業と団体が出展しました。 |

|
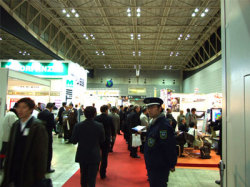
|
救助トレーニング実習 レポート!今回の木村の主な狙いは、同時開催の関連セミナー! これまでは、展示ブースを見るのに精一杯でなかなか参加できなかったもので、今回は同時開催セミナーに初挑戦です。 目当てのセミナータイトルは「災害時における社会貢献「緊急対応チーム」(講義)/CERT救出・搬送トレーニング」。 「救助」というキーワードが気になり、読者の皆様にその内容を伝えなければ!と、参加させていただきました。 (詳しい救助方法につきましては、別ページ(準備中)でご紹介いたします。) しかし行ってみますと… 事前告知されていた時間よりも前倒しで開始されており、私が到着したときには、前半の講義が終了していました。 (講義の様子をお伝えできなくて、申し訳ありません。) しかし、私の狙いは救助トレーニングです。 広いホールの一角にできた人だかりに駆け寄ると、下敷きになった人を道具と人力で救助する訓練が行なわれていました。 そのときバールを持っていたのが女性!ここがポイントです! てこの原理を使えば、女性でも救助活動ができるんですよ! 一通り説明とデモンストレーションが終わり、「じゃぁ、二組に分かれてやりましょう!」の声。 デモンストレーションをちゃんと見られなかった私は、今度こそ積極的に参加しようと意気込んでいると、スタッフの方から「じゃぁ、正面にいるあなた!リーダーやってください」と突然の指名。 ええええええええええええ?! 今来たばっかだのに(TーT) 内心泣きじゃくりながら、お引き受けいたしました。 幸いにもこの時はスタッフの方がクチを出してくださったのと、チームを組んだ皆様がある程度把握していてくださったので、なんとか要領を掴んで、無事救出成功! 細かい方法につきましては、先述の通り、別ページにてご説明いたしますが、大まかには以下の通りです。 1.現状把握&安全確認 救助活動をして2次災害が起きないか、周辺状況を確認します。 2.現状保持 最初の状態から、余震や少しの振動で重量物が動かないよう、現状を保持するためにクサビを入れます。 3.イゲタ組み 角材でテコを使うときの「支点」となる井桁(イゲタ)を組みます。 4.持ち上がったときの段取り 同時に、てこで持ち上がった障害物を支えるもの(角材)を用意しておきます。 5.テコで持ち上げ 作業者全員に安全を確認し、てこで障害物を持ち上げます。 6.「支え」の入れ込み 持ち上がったところで、角材とクサビを挟み込み、障害物を固定します。 7.高さをつけながら繰り返し さらに、てこのイゲタを高くしたり、持ち上げる位置を変えたりしながら、障害物を持ち上げてゆきます。もちろん、支える角材も適宜高くしていきます。 これを繰り返し、下敷きになった人を救出します。 「そんな角材やらクサビが都合よく落ちてるわけないじゃないか!」 と、思われるかもしれません。もちろん私もそう思いました。 そこで考えられることは二つあります! ① 角材・クサビなどを必要なだけ備蓄しておく ② 別のもので代用する ①ができる環境が整っている場合はそうすればいいだけですが、往々にしてスペースなどの問題から①は困難となることが多いでしょう。 「②の他のものって、じゃぁ何?!」 そこもしっかりトレーニングしてまいりましたのでご紹介いたします。 例えば!大抵のオフィスならたくさんある「A4紙の束」!そしてダンボール!です。 角材の代わりに紙の束! クサビの代わりにダンボール!です。 紙が無ければ本でもOK! 表面が滑らないように、布ガムテープやビニールテープを巻きつけておくと作業性も上がりますし、安全です。 代替を利かせにくいのが肝心要の「バール」です。 なぜならバールなどの支柱役には「テコの原理」で非常に大きな力がかかりますので、下手なもので持ち上げると、かえって危険なのです。 「テコの原理で重量物を持ち上げて…よし!クサビを入れよう!…と思ったら、テコが折れた!」 その瞬間、下敷きになっていた人は、クサビを入れようとした人は、どうなってしまうか・・・。 それを考えると、バールの一本を用意して済むなら、その方が圧倒的に安全です。 <作業時の注意点!> ◆持ち上げた重量物は、決して下ろさない! 一度あげたものを下げると、思わぬ二次災害を招くおそれがあります。 ◆クサビは、むやみに打たない! クサビというと、木槌などでガンガン打ち込むイメージがあるかもしれませんが、今回の場合、クサビが何本も使われているので、一箇所だけをガンガン打ち込むと、せっかく安定していた他のクサビが浮いてしまい、重量物が不安定になります。 また、打ち込む振動が、下敷きになっている人に伝達してしまい、負担をかけることがあります。 打ち込む必要があるときは、作業者が共通の認識を持って打ちこむようにしましょう。 ◆重量物の下に手を入れない! クサビを打っていても、余震や加重の以上で崩れることは充分に考えられます。 それを起こさないよう固定することも大事ですし、崩れた場合に怪我をしないよう動くことも重要です。 もちろん、状況によっては止むを得ず、手どころか体を入れ込んでいかなければならない状況も出てきますが、要は、「救助する側がケガをしないように管理しましょう!」ということです。 自己犠牲の気持ちも大事ですが、そこで要救助者もろとも救助者が2次災害に巻き込まれてはもともこもありません。さらに、「多くの命を救助する」という目標を考えたとき、人手・人材は大変貴重です。 さて!今回も長いお話になってしまいましたが、雰囲気は伝わりましたでしょうか! 私としては、今後自治会などで、こういった活動をどんどん推進していけるよう働きかけていくつもりです。 消防にも「心配蘇生法の講習会があるように、救助法の講習会があってもいいのでは?」と投げかけていくつもりです。(後者はどれくらい時間がかかるかわかりませんが^^;) こういった訓練は、理屈は簡単でも、やってみると、結構皆さん焦るもののようです。 訓練を重ねて、要領と理屈を体で覚えておくことが大事ですね! これを読んで、「コメントを書け!」とはいいません。 明日から、何かをしようと腰を上げていただければ、それで充分です。 本日は、長丁場、お付き合いをいただきまして、ありがとうございました! 次回こそ、消防署のお話をします^^; 防災士 木村周吾 |
 ▲多くの方が参加。展示会と同時開催名だけに、作業に向いた服装の方が少なく、より実地的な訓練に。  ▲人だかりのなかでは、軽装の女性がバールを手に、救助活動に当たっていました。  ▲そして、無事救出! ▼二組に分かれて、皆で実習です。 「見てるよりも、やるべし!」訓練の極意。  ▲大人8人が乗った(推定480kg)板の下敷きになった彼を救出。10人程度のメンバーで役割分担して行なう。このときリーダーになった女性の「子供だからやさしく救助しましょう」の一言に、木村感心。  ▲角材とクサビを駆使して、バールで重量物を持ち上げます。「1・2の3!」 ▼持ち上がっている間に、角材とクサビを入れ込み、重量物を支えます。  ▼安全に気をつけながら、これを繰り返し…  ▲無事救出!拍手が上がります!  ▲これらの角材・クサビで基本を訓練しました。 ▼次は、「これらが無いとき」の応用編  ▲角材の代わりに、オフィスでおなじみのコピー紙を使って救出!滑り止めのために布ガムテープを巻きつけています。  ▲クサビの代わりに、ダンボールを折って使いました。コピー紙が入ってたダンボールです。もちろん、無事救出です! ▼日中の被災は、男手が不足することが多く、オフィスであれ地域であれ、「女性の力」が必要とされます。  ▲長いブーツを履いたおしゃれな方も ▼オフィスにいそうなこの方も「てこの原理」を使って、救助活動に参戦できます。  参加された皆様、本当にお疲れ様でした! ありがとうございました! |
コメント
 コメントをする
コメントをする


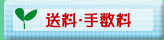


コメントはまだありません。